
企業間の連携には多くのパターンがあり、これらをいくつかの方法で分類してみると、次のようになります。
【企業間の関係での分類】
連携企業間の関係が商売上どのような関係にあるかで分類すると、大きく次の2つのパターンに分類されます。
(1)水平連携
同業者間による製品開発などの連携
(2)垂直連携
メーカーと流通業、小売業などチャネル間での連携
【連携企業の所在地での分類】
それぞれの連携企業が同一地域(都道府県)に存在するかどうかでも分類されます。
【連携の方法、組織形態での分類】
連携の方法、組織として次のようなパターンが考えられます。
業務連携、フランチャイズ、協力会社方式、共同出資会社、共同持ち株会社、合併・分割(吸収分割)などです。また、組合による連携として、事業協同組合、協業組合、企業組合、組合による共同出資会社設立などです。
なかでも注目されるのは、組合による共同出資会社の設立です。組合が出資するため、会員1社あたりの資金リスクは小さく、他産業との連携も図りやすいことが特徴です。パートナー企業から見ても、複数の中小企業の集まりの事業協同組合は、単独企業と比べ、技術力、人材の面で魅力が大きく、有効な連携手法の一つと言えます。
御社の場合は、メーカーで地域での連携を希望されているので、同一県内での水平連携で、まずは業務連携から始められてはいかがでしょうか。その後、連携企業との関係が緊密になる、連携企業が増えるなどの変化があれば、共同出資や組合設立などを検討するのがよいでしょう。
中小企業で企業間連携を行う場合、連携企業および連携企業のほとんどが同一都道府県である場合が多い傾向にあります。なかでも、企業連携をしている企業の方が、収益が好調な傾向にあります(図1:2006年版中小企業白書)。
また、地域の中小企業が、連携をとって新製品開発や経営力の向上を図る試みには、各自治体や各都道府県の中小企業団体中央会で、支援策が講じられています。
さらに、中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)で登録しているアドバイザーが、高度化事業を計画している組合などの基本構想を固め、高度化事業実施計画書の作成や組合などの運営が円滑に進められるよう、必要なアドバイスを行う「企業連携支援アドバイザー」制度があります。
なお、先の垂直的連携の支援策として、わが国製造業を支える基盤技術を担う川上中小企業者と、燃料電池や情報家電などの川下製造業者などの連携、コミュニケーションの円滑化を目指す「川上・川下ネットワーク構築支援事業」を、中小機構が実施しています。
これらの支援策をうまく活用して、製品開発力や技術力、営業力の強化につなげていただきたいと思います。
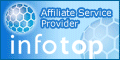





0 件のコメント:
コメントを投稿